
2012
12月3日
平成25年度予算要望

平成24年12月3日、公明党議員団は、 田中大輔中野区長に対し、平成25年度の予算要望を行いました。要望書は区民の皆様からお寄せいただいたご意見・ご要望をもとに、調査・検討を踏まえ区議団として取りまとめたものです。区財政が切迫する中にあっても、断じて区民生活を守るという覚悟の上、真に必要な事業をより効果的、効率的に見直すことが重要です。要望書では、特に防災・減災のための施策、高齢者、障がい者施策に重点を置き、だれもが安全で安心に暮らせる中野を目指して、新たなシステムの導入や個々の事業の存続・改善・拡充をもとめています。
要望書全文はこちら→
11月18日
中野区災害医療救護訓練
 |
 |
 中野区災害医療救護訓練が平和の森小学校体育館で開催されました。訓練には、町会などの地域防災会をはじめ216名の方々が参加され、野方消防署による三角巾を使った応急救護訓練、中野区医師会によるトリアージ(負傷度判定)を想定した医療救護訓練など、さまざまな訓練が行われました。
中野区災害医療救護訓練が平和の森小学校体育館で開催されました。訓練には、町会などの地域防災会をはじめ216名の方々が参加され、野方消防署による三角巾を使った応急救護訓練、中野区医師会によるトリアージ(負傷度判定)を想定した医療救護訓練など、さまざまな訓練が行われました。
こうした訓練を経験しておくことは、いざという時に冷静かつ迅速な対応ができ、大変重要であると実感しました。
今後とも、震災時における医療救護への対応策の強化、地域防災会による救助活動への支援に尽力してまいります。
10月23日
東京都道路整備事業促進大会
 |
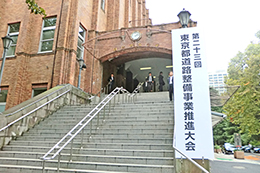 |
東京都道路整備事業促進大会が23日午後、日比谷公会堂(千代田区)で開催され、私も参加いたしました。
今回で23回目を数える同大会は、交通混雑の緩和、安全で快適なまちづくりへ、道路や橋梁、鉄道連続立体交差などの整備推進を図る目的で開催されています。友利春久東京都議会副議長(公明党)の来賓挨拶、代表メンバーによる意見発表の後、大会宣言及び大会決議が満場一致で採択されました。
中野区においては、西武新宿線連続立体交差事業の整備、早稲田通りの拡幅整備などを着実に推進するとともに、無電柱化やコニュミティゾーンの形成を図ることで、災害に強いまちづくりを推進していくことの重要性を改めて実感しました。今後とも災害につよい中野区を目指して、真剣に取り組んでまいります。
10月21日
平成24年度中野区内消防団合同点検
 |
 |
|
 |
 |
平成24年度中野区内消防団合同点検が、江古田の森公園多目的広場で行われました。この合同点検は、中野・野方両消防団によるもので、団員の規律や節度、習熟度などに関する部隊検閲、姿勢や服装などについての通常点検の後、応急救護訓練指導や救助・救護活動を実施。続いて、可搬ポンプ積載車や防災隊による消火活動が行われました。最後に実施された、避難路を確保するための一斉放水は圧巻でした。
来賓として参加した私は、中野区議会を代表して挨拶いたしました。消防団の規律ある訓練を称えるとともに、区議会としても防災対策に全力で取り組んでいく決意を述べさせていただきました。消防団員の皆様の気概あふれる姿に接し、私も、災害に強い中野のまちを築いていこうと、さらに決意を固めました。
10月1日
決算特別委員会にて総括質疑

平成24年第3回中野区議会定例会の決算特別委員会で、一問一答形式による総括質疑を行いました。決算審査は区政を支出面からチェックする大事な議会の役割です。予算が適切に支出されたか、また、さらなる効率化が図れないか、さらに区民サービスの向上に向け、制度の見直しや新規事業の必要性など、幅広い議論が行われます。私に与えられた質疑応答時間は90分間。公明党議員として、“生活者の目線”から区政の在り方をただしました。これからも、区民の皆さまからの負託にお応えするため、全力で働いてまいります。
10月7日
中野区商店街連合会「観光まち歩きシンポジウム」
 |
 |
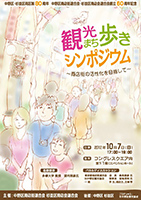 中野区商店街連合会の創立60周年を記念した「観光まち歩きシンポジウム」がコングレスクエアのコンベンションホールで開催されました。会場は先日開業したばかりの中野セントラルパーク「コングレスクエア」です。
中野区商店街連合会の創立60周年を記念した「観光まち歩きシンポジウム」がコングレスクエアのコンベンションホールで開催されました。会場は先日開業したばかりの中野セントラルパーク「コングレスクエア」です。
中野区長などの挨拶の後、多摩大学大学院教授の望月照彦氏による「まち歩きで商店街活性化」をテーマとした基調講演や、商店街の現状や未来像などについてのパネルディスカッションが行われました。
中野駅周辺地区では今後、一層の基盤整備が進められますが、それに伴う商店街の活性化も大変重要な課題だと改めて痛感しました。
10月6日
「市民後見人養成講座」を受講
 |
 |
東京大学主催の市民後見人養成講座を受講致しました。初回は、講座の目的や流れの説明、何人かの受講生による受講動機などのスピーチ、法定後見の事例を通しての実務学習などが行われました。 成年後見制度については、議会でさまざまな角度から取り上げてきましたが、認知症や障がい者の権利、財産を守るためには、同制度の一層の充実が不可欠と痛感しています。今回の講座受講を通して、成年後見制度の知識や実務をしっかりと学び、区民生活の向上に役立ててまいる決意です。
9月13日
なかの里・まち連携宣言式

群馬県みなかみ町と中野区との「なかの里・まち連携宣言式」が、13日午前10時から中野区役所で行われました。私も中野区議会建設委員長として参加させていただきました。
「なかの里・まち連携事業」とは、①人を結ぶ体験・観光交流②暮らしを結ぶ経済交流③自然を守る環境交流――の3つを柱とした、自治体間の交流枠を超えた民間活力を活用した連携事業で、平成21年から始まりました。これまで福島県喜多方市、茨城県常陸太田市、千葉県館山市、山梨県甲州市と連携。みなかみ町は5番目となりました。
式典では連携宣言の後、署名交換が行われ、田中大輔中野区長と岸良昌みなかみ町長が固い握手。調印式は盛大な拍手のなか終了しました。
この日、区役所前広場では、新たな連携自治体の参加を記念して物産展が開かれ、さっそく出店した「みなかみ町」のブースに多くの人が訪れていました。
中野区では今後、こうした物産展での交流をはじめ、みなかみ町への観光ツアーや体験型のモデル事業などを実施していく予定です。これからも「なかの里・まち連携事業」の推進に尽力してまいります。
9月11日
「遠位型ミオパチー」について意見交換

中野区議会公明党として「遠位型ミオパチー患者会」代表代行の織田友理子さんの表敬訪問を受け、「ウルトラオーファンドラック」開発支援のため法整備の必要性などについて、患者会の皆様の切実な声を聞かせて頂きました。
「遠位型(えんいがた)ミオパチー」とは、体幹部より遠い部分から徐々に筋力が低下していく筋肉の進行性難病。ミオパチー(Myopathy)とは筋肉の疾患を表す総称で非常に多くの病気を含んでいます。例えば、筋ジストロフィーもミオパチーの一種です。ウルトラ・オーファンドラッグとは、患者が特に少ない希少疾病用医薬品のことで、国が積極的にその開発について促進・支援する必要があります。
遠位型ミオパチー治療薬が一日も早く患者に届くよう、治療新薬開発を早期に実現するために自治体からの要望書の国に提出すること、また、研究費の増額や難病指定・特定疾患の認定など、公明党のネットワークを活かして国に働きかけていきたいと思います。また、患者会が行っているこの病気を啓蒙するために行われている劇の公演や、署名活動などについて、出来得る限り、サポートしてまいりたい。
8月30日
特別区議会議員講演会

飯田橋にある東京区政会館で行われた特別区議会議員講演会に参加いたしました。
講演会では、「公共施設老朽化とシティ・マネジメント」と題し、東洋大学教授の根本祐二氏による講演が行われました。公共施設の老朽化問題の処方箋として、シティ・マネジメント(公共施設マネジメント、インフラ・マネジメント、ファイナンス・マネジメント)が有効であるという趣旨の内容でした。「マネジメント」とは、さまざまな資源や資産・リスクなどを管理し、経営上の効果を最適化しようとする手法のことです。
中野区でも学校施設等の建て替えの問題がありますが、財政面での民間資金の活用や構造面での長寿命化など、さまざまな取り組みが必要と考えます。今後、区内公共施設の老朽化の問題に真剣に取り組んでまいる決意です。
8月1日
中部すこやか福祉センター視察

中野区議会の地域支えあい推進特別委員会のメンバーとして、中央3丁目の中部すこやか福祉センターを視察しました。上高田、桃園、東部、昭和、東中野の5つの区民活動センターの運営委員会会長にもお越しいだだき、地域の見守り支えあいに関する意見交換会を行いました。地域での見守り・支えあいに対する関心の高まりや、すこやか福祉センターとの交流推進を望む声など、貴重なご意見を伺うことができました。
その後、センター内を見て回った際、3階に併設されている就労支援事業所では、精神障がいの方々の就労に向けた取り組みが行われていました。見守り・支えあいには、高齢者のみならず、さまざまな状況の方々に対しても十分な対策を取らなければならないことを改めて実感しました。
7月23日・24日
静岡市、浜松市視察
中野区議会公明党として静岡県・静岡市、浜松市を訪問・視察してまいりました。23日は、静岡市の再開発事業の取り組みを視察してきました。静岡市は、低層の木造建築物が密集するなど、さまざまな問題を抱える中、①細分化された宅地の統合②不燃化された共同建築物の建築③公園、緑地、広場、街路などの公共施設の整備と有効なオープンスペースの確保を、一体的・総合的に進める市街地再開発事業を展開してきました。
 |
 |
 |
また、JR静岡駅の北口駅前広場はかつて、たまり空間が歩行者に利用しにくい(わかりにくい)位置にあったり、地下への出入口階段の幅員が狭く、暗い空間となっていたりするなど、多くの課題がありましたが、整備事業により、バリアフリー化が進められ、地上と地下を結ぶ円形の吹き抜けのある、大屋根付きの中央広場が建設されるなど、さまざまな工夫により賑わいを取り戻していました。
中野区の木造密集地域やJR中野駅地区整備における課題に対し、大変参考になる視察となりました。
 |
 |
また24日は、浜松市の市立中央図書館を訪問し、同市の先駆的な図書館行政について説明を受けました。浜松市には21館1分室の図書館がありますが、今年、2館で指定管理者制度を導入。指定管理者制度とは、従来、出資法人などに限定されていた「公の施設」の管理を、民間事業者も含めた幅広い団体に行わせる制度です。これにより同市は柔軟な人員配置が可能となり、事業経費の削減につながっているそうです。また、平成17年に蔵書管理をバーコードからICタグへ切り替えたことで、貸出の待ち時間短縮や蔵書点検期間の短縮が図られたそうです。
指定管理者制度やICタグの導入は、中野区でも今後、検討課題になると思います。浜松市などの取り組みを参考に、さらに研究してまいります。
7月17日・18日
京都の小学校視察
7月17日、18日の2日間にわたり、中野区議会公明党議員団として京都市の小学校を視察してまいりました。
 |
 |
まず、初日は京都市立朱雀第四小学校を訪れ、同校の「エコ改修と環境教育事業」の状況を見て回りました。校舎はグリーンカーテンや、京町家を思わせる庇(ひさし)が設置され、直射日光を遮るとともに、美しい景観を保っていました。
 |
 |
共有スペース「あかしやホール」は広々とした空間が確保され、可動式畳ユニットや間伐材での丸太椅子が自由に利用できるようになっていました。児童と地域住民との憩いの場としても活用されているそうです。「あかしやホール」を抜けると自然と親しめる「いのちの庭」へ。芝生の丘、せせらぎ、池、水田などが整備されており、環境教育の拠点になっていました。
京都市視察の2日目(18日)は、私立立命館小学校を訪問させていただきました。
 |
 |
同小学校では、子どもたちは8時10分までに登校。8時25分から「モジュール・タイム」が始まります。「モジュール・タイム」とは毎朝30分間、英語や国語の音読、100マス計算などをスピード、テンポ、タイミングを重視して行い、脳を活性化させ、集中力や学習効果を高める取り組みです。元気な声が校舎中に響き渡っていました。
また、低学年は1日の終わりに、学んだことを反復する「寺小屋の時間」を設けています。基礎、基本の学力を定着させる効果を狙った取り組みです。視察した時は、芸術や音楽の「本物」に触れる体験を通じて、豊かな感性や自己表現力を養う試みも行っていました。
中野区の学校施設についても、今後、建て替えや長寿命化を検討していく中で、環境教育事業を取り入れなければならないこと、また、学力の向上や豊かな感性を育む取り組みなど、さらなる工夫が必要だと痛感いたしました。
7月1日(日)
中野駅地区第1期整備事業完成式典
 |
 |
 中野駅地区第1期整備事業の完成式典に参加させていただきました。
式典は完成したての中野通りを跨ぐ東西連絡路の橋上スペースで行われました。田中大輔・中野区長をはじめ来賓の方々の挨拶や、第1期整備事業のこれまでの経過報告の説明の後、式典を祝して「くす玉割り」が行われました。私も区議会建設常任委員長として引手に加わりました。
中野駅地区第1期整備事業の完成式典に参加させていただきました。
式典は完成したての中野通りを跨ぐ東西連絡路の橋上スペースで行われました。田中大輔・中野区長をはじめ来賓の方々の挨拶や、第1期整備事業のこれまでの経過報告の説明の後、式典を祝して「くす玉割り」が行われました。私も区議会建設常任委員長として引手に加わりました。
今後、中野駅地区の更なる発展のためには、中野駅新西口改札の南北自由通路を始めとする第2期整備事業や新北口駅前広場などの第3期整備事業を着実に推進しなくてはなりません。さらなる乗降客の増加を見通して、中野駅地区の活性化や利便性の向上のために、これからも全力を尽くしてまいります。
6月26日(火)
住宅型有料老人(群馬県・高崎市)ホームを視察
 |
 |
|
| 音楽療法の実施風景 |
公明党中野区議団として、群馬県高崎市にある住宅型有料老人ホーム「シニアホーム サウンド」を視察しました。併設する「デイ・ニューサウンド」では、認知症予防や言語障害の回復につなげようと音楽療法を導入したデイサービスを行っています。音楽療法の実施風景も見させていただきましたが、常勤講師の指導のもと、利用者はタンバリンや打楽器などを使って、歌ったり体を動かしたりして、大変楽しそうでした。また、老人ホームの近くには通所施設も開設していました。今回の視察を通して、認知症などの予防対策や介護施設のソフト面での充実に取り組んでいく必要性を痛感しました。
超高齢社会に突入した日本。課題はたくさんありますが、皆さまが長寿を満喫できる地域づくりをめざし、全力で取り組んでまいります。
6月5日(火)
杉並区立井草中学校視察
 |
 |
 |
 |
中野区議会公明党として、杉並区の井草中学校を視察いたしました。同校は耐震診断の結果、「補強」でなく、「改築」が望ましいとの指摘を受けて、平成21年秋からの仮設校舎建設に続き、新校舎の工事が進められ、昨年末にA・B棟が完成。今年1月より新校舎での授業が始まりました。特別支援学級が入るC棟の工事も8月末には完成の予定です。改築に際しては、すべての人にやさしい「ユニバーサルデザイン」と環境を考慮した「エコスクール」を導入しています。校舎棟を中心に自然換気サッシやクールヒートトレンチ(地中熱利用)、内装の木質化、屋上緑化、雨水利用などが施されていました。 また防災拠点としての機能を充実させるとともに、太陽光パネルも設置し電力の一部に活用していました。新体育館は、すべての照明をLEDにしたことで、従来の水銀灯に比べ約40%の消費電力を削減しています。これまで時間がかかっていた点灯も、すぐに点くようになっていました。今後の中野区の重要課題である学校再編においても、ソフト・ハード両面で、子どもたちのために最善の教育環境を整備しなければならないと実感致しました。
6月1日(金)
中野区伝統工芸展
今年で21回目となる中野区伝統工芸展が、区勤労福祉会館(中野2丁目)で開催され、私も視察してまいりました。
 |
 |
 |
 |
昔から人々の暮らしの中で育まれ、長い年月をかけて磨き抜かれてきた伝統工芸。中野で活躍する作家の伝承の技と作品は、いずれも心がほっとする温かさを感じました。和装品や彫刻、陶芸、装飾品など、さまざまなブースがあり、匠の技を間近で見ることのできる実演コーナーもありました。中でも手描友禅の実演では繊細な筆使いに感心させられました。展示品は色が鮮やかでデザインの優れた作品ばかりで、魅了されました。また抹茶コーナー(有料)もあり、裏千家の御手前を堪能できました。
今回、伝統工芸展を拝見して痛感したことは、後継者不足が問題となる中で、こうした素晴らしい技術や技の継承を、途切れさせてはならないということです。中野区の伝統文化の発展を推進するとともに、伝統技術の後継支援に尽力していきたいと、決意を新たにしました。
5月28日(月)
西武新宿線踏切渋滞解消のための期成同盟決起大会

西武新宿線の踏切渋滞解消のための期成同盟決起大会が28日午前、野方区民ホールで開催されました。私は、5月1日の期成同盟の理事会で同会の副会長に選任され、今回は副会長の立場で参加いたしました。
西武新宿線の中井駅~野方駅間は、「まちづくり勉強会」など地域住民の活動が推進力となり、昨年8月に連続立体交差事業の都市計画決定がなされ、今年度は工事着工のための事業認可を受ける準備が進行中です。それと同時に、事業候補区間となっている野方駅以西(~井荻駅間)の連続立体交差化についても、早期実現が求められています。
決起大会は、これまでの経緯を踏まえ、中井駅~野方駅間の着実な事業の推進と野方駅以西の早期実現を目指す熱気溢れるものとなり、最後に大会宣言と決議文を満場一致の大拍手をもって採択しました。
「開かずの踏切」解消のため、そして安全・安心のまちづくりのために、これからも全力を尽くして参ります。
5月19日(土)
JR中野駅北口改札リニューアルオープン
 |
 |
JR中野駅の北口改札がリニューアルオープンしました。 これまで北口改札は中野通り側に設置されていましたが、数段の階段があり、バリアフリーになっていませんでした。 これを解消するため、8番線ホーム下の壁(北側の壁)を取り除き、直接サンモール商店街側に改札口を設置して歩行者動線を切り替えました。 改札の切り替えに合わせて、新たな改札窓口や券売機室などの施設ができるほか、車イスの方などもスムーズに利用できるよう、中野通り側から改札口に向けてスロープも設置されました。 改札切り替え後も北口駅前広場や東西連絡路の整備工事は引き続き行われ、全体の完成は6月下旬頃の予定です。 北口改札のバリアフリー化については、公明党議員団として長年要望してまいりました。今回、実現の運びとなり、議員としての責務を一つ果たすことができたと感じています。 暮らしやすい中野区にしていくため、これからも全力を尽くしてまいります。
5月18日(金)
中野区合同水防訓練
 |
 |
中野区合同水防訓練が5月18日、江古田の森公園の多目的広場で行われ、南かつひこも参加させていただきました。 水防訓練には野方・中野の消防署、消防団、区職員をはじめ、町会・自治会、自主防災組織、災害時支援ボランティアなどが参加。東京ガスなど民間企業の協力も得て、本番を想定した本格的な訓練となりました。 主な訓練として、水防資器材の搬送訓練や浸水家屋からの救出・救助活動が行われたほか、積土のう工法や、連結水のう工法、簡易水防工法が実演されました。 またガス漏れ防止訓練や住民避難誘導訓練も実施されました。 最近、竜巻や雷雨など天候の激変による大きな被害が相次いでいます。今回の水防訓練を通し、いざという時のためにも訓練は欠かせないと改めて実感しました。 南かつひこは平成17年9月の妙正寺川の氾濫による甚大な被害を教訓に、台風や集中豪雨による河川の増水や住宅への浸水、がけ崩れなどの防止対策に取り組んできましたが、今後とも実践的な水防訓練を支援するとともに、水害対策の一層の強化に尽力してまいります。
4月1日(日)
「中野四季の森公園」開園式
 |
 |
旧警察大学校等跡地に「中野四季の森公園」(中野4丁目13番地)が開園しました。開園式典には私も出席させていただきました。「中野四季の森公園」は、JR中野駅から徒歩5分という場所にあり、広さは1.5ヘクタール。甲子園球場のグラウンド面積(1.47ヘクタール)とほぼ同じ広さです(平成27年度には、さらに0.6ヘクタール拡張される予定)。 公園は、芝生が敷き詰められた多目的広場、透水性舗装が施された園路をはじめ、池や噴水、ベンチ、時計塔などが整うほか、管理棟には、多目的スペースや授乳スペース、トイレなどが整備されています。区民の新たな憩いの場として、中野区を象徴するスポットとして好評を博しています。
1月8日(日)
野方消防団始式

野方区民センターで行われた野方消防団始式に出席させていただきました。
式典では、昨年一年の消防団の活躍に対するさまざまな表彰や消防団長訓示、中野区長告辞、新入団員紹介などが行われました。
消防団員の皆様は普段は生業を持ちながら、訓練を行い、地域防災の要として活動されています。中野区の安全・安心のため昼夜を問わず対応される消防団員の皆様に心より敬意を表します。
昨年の3・11以来、私たちの防災に対する意識は大いに高まりました。一人一人がいざという時に備えて、平時から共助の精神で見守り、支え合うことの大切さを痛感しております。その支え合いの重要な柱が地域防災を担う消防団です。今年も、中野区民の安全・安心が確保されるよう、消防団員の皆様のご健勝をお祈り申し上げます。
1月4日(水)
中野区賀詞交歓会

中野区賀詞交歓会が中野サンプラザで行われました。役所が仕事始めとなるこの日、区長以下区役所幹部、地域の各団体関係者、区議会議員、ご来賓の皆さまなどが一堂に会し、新年の出発をいたしました。
中野区長、区議会議長、ご来賓の方よりご挨拶があり、その後懇談となりました。多くの参加者にご挨拶しながら、課題が山積する区政に対して、気を引き締めて臨む決意をいたしました。